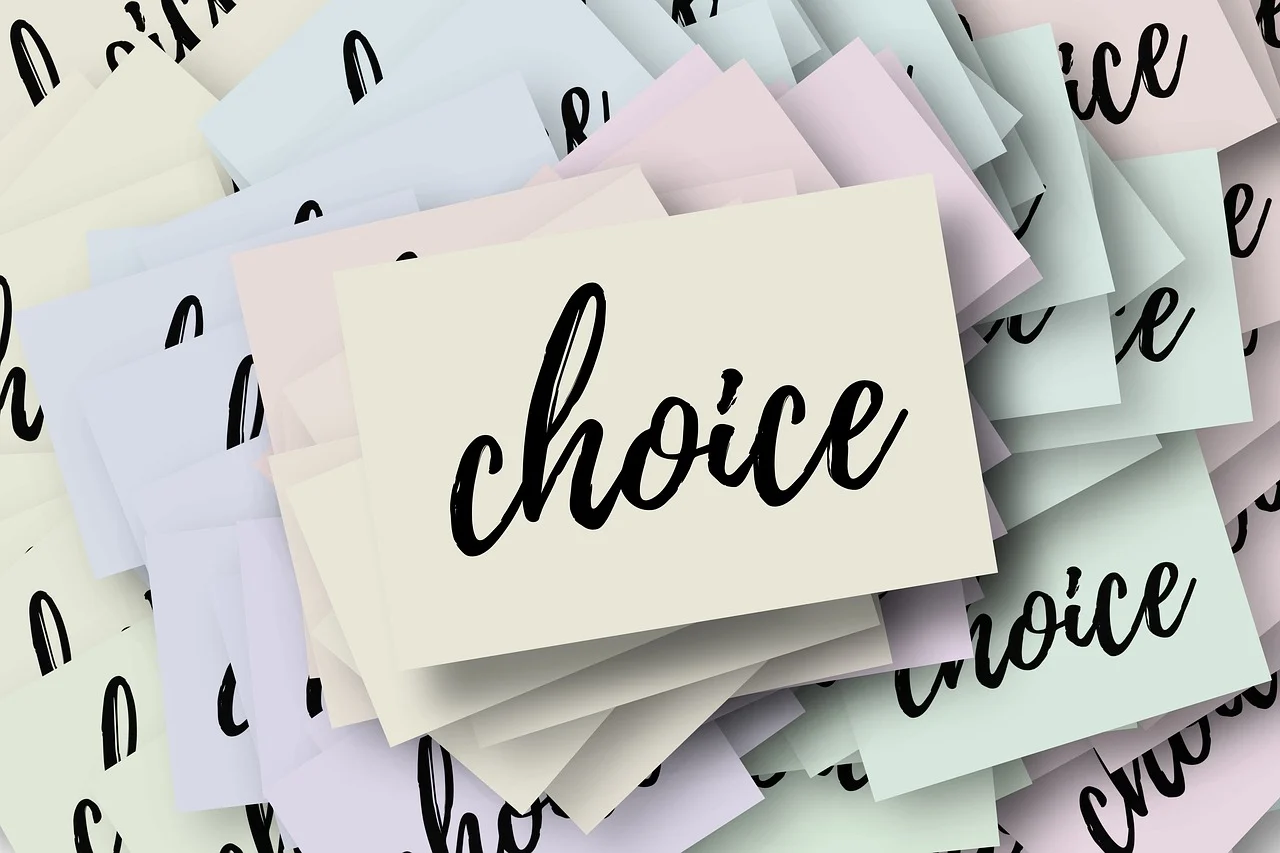勉強で大事なのは才能か努力か 青山先生の考え
努力か才能か、どんな世界でもよく言われることですが、京都大学工学部物理工学科3回生 青山先生の考えをご紹介します。

勉強で大事なのは才能か努力か
この議論は常にされているように感じますが、私の見解を述べたいと思います。結論から言うと努力です。
確かに才能の差というものは少なからずあります。教科書の内容をすぐに理解できる人もいるし、なかなか理解できずに苦労する人もいます。ただ、どんなに才能のある人でもその差は努力で簡単にひっくり返されると思います。今回このタイトルを選んだ理由の1つに、「才能がない」と思い込んでいる人を目にすることがあるということがあります。ただ、勉強において恐ろしく才能がある人というのはごく一部であり、大半の人において大切になるのは努力です。受験という、範囲の限られた中での勝負であれば尚更です。
才能の無さを「諦める理由」にするのはもったいないし、逆に才能があることが「やらなくていい理由」にもなりません。
結局は努力した方が勝ちます。才能がないかも、、、と思っても悩む必要はありません。どうしたら才能のある人に勝てるかを考えて(そもそも才能がある人はごく一握りなのでこの人たちに必ずしも勝たなくても良いのですが・・・)努力すれば必ず結果はついてきます!【学園長追記】 大学受験は知識とスピード勝負
学園長出谷も、青山先生の意見に強く同意します。特に、小学校、中学校、高校とステップアップする毎に知識量が急速に増えていくため、「知っていたら解ける一方、知らなかったら解けない」という問題がどんどん増えていきます。
小学校の図形問題で、どこに補助線を引くのか?という問題は才能に左右されところがあると思います。
私はそういった問題は苦手でした・・・。が、大学受験ともなるとほとんど、知識量に加えて速度と精度(ミスをしないこと)の勝負になります。そうなると才能だけで戦える人はいなくなります。
良い成績を取るのはほぼ全員が人より沢山の問題を解いている人です(同じ問題を何度も解き直すという事も大切です)。共通テストの科目や分量が増える一方であることを考えると、今後ますます速度と精度が求められていくのではないでしょうか。
人間は忘れる生き物なので、やればやるほど「また間違えたやん・・・」と自分に落胆することも増えてきます。向いてないかも・・・なんて弱気になることもあると思います。ただ、ほとんど全ての人は才能がありません!
1・2問出来るようになっても急には結果に表れませんが、ある程度網羅出来てくると点数も安定して伸び始めます。辛抱強く努力を続けましょう!